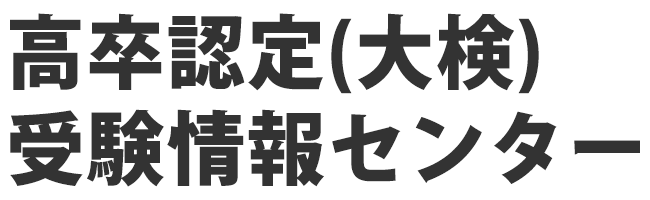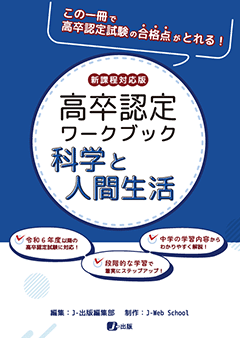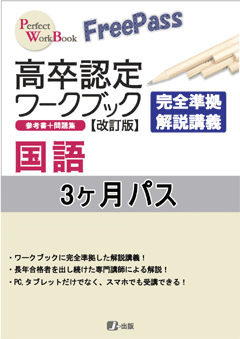高卒認定情報コーナー
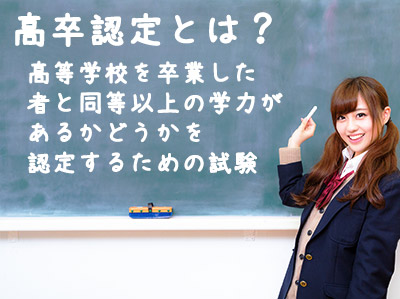
1高卒認定要件
受験年度の3月31日までに満16歳以上になる方であれば、どなたでも受験できます。(ただし、既に大学入学資格を持っている方は受験することができません)
2005年度から、全日制高等学校等に在学されている方も受験が可能となりました。
2高卒認定試験願書出願期間と出願方法
| 高卒認定願書出願期間 | ||
|
第1回(8月試験)
2024年4月1日(月)~5月7日(火) 5月7日(火曜日)の消印有効 第2回(11月試験) 2024年7月16日(火)~9月6日(金) 9月6日(金曜日)の消印有効 |
||
| 試験実施日 | ||
|
第1回(8月試験)
2024年8月1日(木)・2日(金) 第2回(11月試験) 2024年11月2日(土)・3日(日) |
||
| 出願書類の提出(願書・履歴書は各都道府県の教育委員会担当課にあります。) | ||
|
高卒認定受験案内に添付してある封筒を使用し、文部科学省あてに書留で郵送してください。
(※持参による願書受付は行いません。) ○ 高等学校卒業程度認定試験についての問合せ先 文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課認定試験第一係・第二係 電話:03-5253-4111(内線2024・2643) |
||
| 受験料 | ||
■ 7科目以上9科目以下 8,500円 ■ 4科目以上6科目以下 6,500円 ■ 3科目以下0●●●● 4,500円 |
||
3出願書類
| 高卒認定試験出願書類 | |
|---|---|
| 書類不足や出願内容に誤りなどの不備がある場合は受理されませんので注意するようにして下さい。不備が解消されない場合は不受理となり、受験できなくなりますので注意して下さい。 | |
| ① 受験願書 |
●
受験案内の「受験願書等の記入方法」を参照
※黒の鉛筆(HB以上の濃さ)で記入する。 |
| ② 受験料 |
●
受験科目数に応じた収入印紙を願書の所定の欄に貼る。消印はしないこと(収入印紙は郵便局で購入できます)。
●
都道府県の収入証紙、現金、切手及び小為替等は不可
●
一度受理された受験料は返還されません。
※
免除申請をする科目については受験料はかかりません。
|
| ③ 写真2枚(同じもの) 白黒でも可 |
●
出願前6ヶ月以内に撮影した無帽・正面上半身のもの。
●
サイズは縦4cm、横3cm)
●
写真の裏面に氏名及び受験地の都道府県を記入し、受験者票(控)と受験票の所定の欄に貼り付けてください。
●
カラーコピー及び自宅で印刷した不鮮明な写真は不可
|
| ④ 住民票又は戸籍抄本 (初めて受験する方や過去に合格科目のない方) 本籍地記載のもの |
●
初めて受験する方など、科目合格通知書が交付されていない方は住民票又は戸籍抄本を提出する。
●
出願者本人のみが記載されているもの。
●
出願前6ヶ月以内交付のもの。
●
コピー及び認証印の無いものは不可。
●
外国籍の方は、外国人登録原票記載事項証明書。
※
海外在住の外国籍の方等、上記書類の提出が困難な場合は事前に文部科学省に問い合わせが必要となります。
|
| ⑤ 科目合格通知書 (一部科目合格者のみ)※氏名や本籍地に変更があった場合は戸籍抄本が必要となります。 |
●
過去に大検又は認定試験で合格した科目がある方は、科目合格通知書の原本(コピー不可)を提出する。(紛失された場合には下記再交付願にて再交付の手続きを行ってください。)
●
科目合格通知書を提出する場合は住民票等の書類は不要。ただし前回の受験後、氏名や本籍に変更があった場合は、戸籍抄本を添付することとなります。
●
科目合格通知書を提出することにより、科目合格通知書に記載されている合格科目及び免除科目についての受験が免除されます。
|
| ⑥ 試験科目の一部免除に必要な書類(試験科目の免除を申請する方のみ) |
●
「試験科目の一部免除」を参照し、必要な書類(単位修得証明書、技能審査の合格証明書等)を願書に添付。
●
「証明書類と現在の氏名が異なる場合には、必ず戸籍抄本を添付。
|
| ⑦ 特別措置申請書・診断書 (希望者のみ) |
●
身体障害者受験特別措置希望者は、特別措置申請書と診断書を提出する。(記入方法は受験願書の「身体上の障害等にかかる特別措置」を参照してください。)
●
出願受付後に特別措置の申出があっても、会場等準備の都合上対応できないので、必ず出願書類と併せて提出すること。
●
診断書等を取得するために時間がかかり、出願時に間に合わない場合は個別に文部科学省に相談する必要があります。
|
| ⑧ 出願用封筒 |
●
受験地、住所及び氏名を裏面所定の欄に記入する。
●
同封した書類について、裏面にチェックを入れる。
※
ボールペンで記入すること。
|
4試験の時間割
| 時間割(令和6年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注1
平成27年度試験より「科学と人間生活」及び「物理基礎」の時間割が変更となっておりますので、注意してください。
注2
自分が出願した科目(受験票に記載されている科目)しか受験できません。出願と異なる科目を受験した場合には、その解答は無効となります。特に、同じ試験時間で行う異なる科目に注意してください。(1日目の2時限目「現代社会」と「政治・経済」、2日目の2時限目「日本史(A・B)」、と「地理(A・B)」)
注3
世界史(A・B)」、「日本史(A・B)」、「地理(A・B)」については、A又はBのどちらか1科目しか受験できません。AとBのどちらを受験するかは、試験当日に配付された試験問題を見てから選択することになります。
注4
上記の各科目の時間は試験時間(解答する時間)です。入室時間に注意してください。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
5受験科目
(1) 合格要件
| 教 科 | 科 目 | |
|
国 語
|
国 語 | |
|
歴史
|
歴史 | |
|
地理
|
地理 | |
|
公共
|
公共 | |
|
数 学 |
数学I | |
|
理 科 |
科学と人間生活 | ※合格要件① 「科学と人間生活」の1科目と、 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」のうち いずれか1科目の合計2科目 ※合格要件② 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」のうち いずれか3科目 ※合格要件③ 「物理基礎」「化学基礎」「生物基礎」「地学基礎」4科目 |
| 物理基礎 | ||
| 化学基礎 | ||
| 生物基礎 | ||
| 地学基礎 | ||
| 外国語 | 英語 | |
|
<合格に必要な科目数> ・8科目:必修科目+選択科目(理科の合格要件①を選択した場合) ・9科目:必修科目+選択科目(理科の合格要件②を選択した場合) ・10科目必修科目+選択科目(理科の合格要件③を選択した場合) |
既に合格している科目を再度受験すること、合格に必要な科目数を超えて受験することはできません。
高等学校の単位認定のためにこの試験を受験する場合であっても、上記の試験科目数を超えて受験することはできません。
今年度、大学入学資格検定から高等学校卒業程度認定試験に試験制度が変更されたことに伴って、平成16年度までの合格科目及び免除科目をもって、高等学校卒業程度認定試験の全科目合格の要件を満たしている場合には、「受験案内」49ページ「高等学校卒業程度認定試験の合格について」の申請により合格者となることができます(ただし既に大学入学資格検定に合格しているものを除く)。
詳しくは受験案内30ページの「科目合格者の単位(科目)修得等による合格の申請手続」を参照して下さい。
| (2) 出題範囲 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
高等学校卒業程度認定試験の出題範囲は以下のとおりです。 なお、出題は全て高等学校の新学習指導要領の科目(平成24年度以降の高等学校入学者が使用している教科書の科目)に対応しています。 |
||||||||||||||||||||||||
|
6受験科目の一部免除
| 平成24年4月以降に入学した者 | |||
| 免除をする 試験科目 |
高等学校の 履修科目 |
免除に必要な 修得単位数 |
備考 |
|
国語 |
国語表現Ⅰ |
2 |
平成25年3月までに入学した者。どちらか1科目で免除 |
| 国語総合 |
4 |
||
| 国語総合 |
4 |
平成25年4月以降に入学した者 | |
| 世界史A |
世界史A |
2 |
|
| 世界史B |
世界史B |
4 |
|
| 日本史A |
日本史A |
2 |
|
| 日本史B |
日本史B |
4 |
|
| 地理A |
地理A |
2 |
|
| 地理B |
地理B |
4 |
|
| 現代社会 |
現代社会 |
2 |
|
| 倫理 |
倫理 |
2 |
|
| 政治・経済 |
政治・経済 |
2 |
|
| 数学 |
数学Ⅰ |
3 |
|
| 理科総合 |
科学と人間生活 |
2 |
|
| 物理Ⅰ |
物理基礎 |
2 |
|
| 化学Ⅰ |
化学基礎 |
2 |
|
| 生物Ⅰ |
生物基礎 |
2 |
|
| 地学Ⅰ |
地学基礎 |
2 |
|
|
英語 |
オーラル・コミュニケーションⅠ |
2 |
平成25年3月までに入学した者。どちらか1科目で免除 |
| 英語Ⅰ |
3 |
||
| コミュニケーション英語Ⅰ |
3 |
平成25年4月以降に入学した者 | |
| 平成15年4月以降に入学した者 |
|||
| 免除をする 試験科目 |
高等学校の 履修科目 |
免除に必要な 修得単位数 |
備考 |
|
国語 |
国語表現Ⅰ |
2 |
どちらか1科目で免除 |
| 国語総合 |
4 |
||
| 世界史A |
世界史A |
2 |
|
| 世界史B |
世界史B |
4 |
|
| 日本史A |
日本史A |
2 |
|
| 日本史B |
日本史B |
4 |
|
| 地理A |
地理A |
2 |
|
| 地理B |
地理B |
4 |
|
| 現代社会 |
現代社会 |
2 |
|
| 倫理 |
倫理 |
2 |
|
| 政治・経済 |
政治・経済 |
2 |
|
|
数学 |
数学基礎 |
2 |
どれか1科目で免除 |
| 数学Ⅰ |
3 |
||
| 工業数理基礎(※) |
2 |
||
|
理科総合 |
理科基礎 |
2 |
どれか1科目で免除 |
| 理科総合A |
2 |
||
| 理科総合B |
2 |
||
| 物理Ⅰ |
物理Ⅰ |
3 |
|
| 化学Ⅰ |
化学Ⅰ |
3 |
|
| 生物Ⅰ |
生物Ⅰ |
3 |
|
| 地学Ⅰ |
地学Ⅰ |
3 |
|
|
英語 |
オーラル・コミュニケーションⅠ |
2 |
どちらか1科目で免除 |
| 英語Ⅰ |
3 |
||
| 平成6年4月から平成15年3月までの間に入学した者 |
|||
| 免除をする 試験科目 |
高等学校の 履修科目 |
免除に必要な 修得単位数 |
備考 |
|
国語 |
国語Ⅰ |
4 |
両方必要 |
| 国語Ⅱ |
4 |
||
| 国語Ⅰ |
4 |
全て必要 | |
| 現代文 |
2 |
||
| 古典Ⅰ |
3 |
||
| 世界史A |
世界史A |
2 |
|
| 世界史B |
世界史B |
4 |
|
| 日本史A |
日本史A |
2 |
|
| 日本史B |
日本史B |
4 |
|
| 地理A |
地理A |
2 |
|
| 地理B |
地理B |
4 |
|
| 現代社会 |
現代社会 |
4 |
|
| 倫理 |
倫理 |
2 |
|
| 政治・経済 |
政治・経済 |
2 |
|
|
数学 |
数学Ⅰ |
4 |
どれか1科目で免除 |
| 数学Ⅱ |
3 |
||
| 数学A |
2 |
||
| 工業数理(※) |
2 |
||
| 理科総合 |
総合理科 |
4 |
|
|
物理Ⅰ |
物理ⅠA |
2 |
どちらか1科目で免除 |
| 物理ⅠB |
4 |
||
|
化学Ⅰ |
化学ⅠA |
2 |
どちらか1科目で免除 |
| 化学ⅠB |
4 |
||
|
生物Ⅰ |
生物ⅠA |
2 |
どちらか1科目で免除 |
| 生物ⅠB |
4 |
||
|
地学Ⅰ |
地学ⅠA |
2 |
どちらか1科目で免除 |
| 地学ⅠB |
4 |
||
|
英語 |
英語Ⅰ |
8 |
免除には左記の単位数以上が必要 |
| 英語Ⅱ | |||
| オーラル・コミュニケーションA | |||
| オーラル・コミュニケーションB | |||
| オーラル・コミュニケーションC | |||
| リーディング | |||
| ライティング | |||
| 昭和57年4月から平成6年3月までの間に入学した者 |
|||
| 免除をする 試験科目 |
高等学校の履修科目 | 免除に必要な 修得単位数 |
備考 |
| 国語 | 国語Ⅰ | 4 |
両方必要 |
| 国語Ⅱ | 4 |
||
| 世界史B | 世界史 | 4 |
|
| 日本史B | 日本史 | 4 |
|
| 地理B | 地理 | 4 |
|
| 現代社会 | 現代社会 | 4 |
|
| 倫理 | 倫理 | 2 |
|
| 政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
|
| 数学 | 数学Ⅰ | 4 |
どれか1科目で免除可能 |
| 数学Ⅱ | 3 |
||
| 代数・幾何 | 3 |
||
| 基礎解析 | 3 |
||
| 微分・積分 | 3 |
||
| 確率・統計 | 3 |
||
| 工業数理(※) | 2 |
||
| 理科総合 | 理科Ⅰ | 4 |
|
| 物理 | 物理 | 4 |
|
| 化学 | 化学 | 4 |
|
| 生物 | 生物 | 4 |
|
| 地学 | 地学 | 4 |
|
| 英語 | 英語Ⅰ | 9 |
免除には左記の単位数以上が必要 |
| 英語Ⅱ | |||
| 英語ⅡA | |||
| 英語ⅡB | |||
| 英語ⅡC | |||
昭和48年4月から昭和57年3月までの間に入学した者 |
|||
| 免除をする 試験科目 |
高等学校の科目 | 免除に必要な修得単位数 | 備考 |
| 国語 | 現代国語 | 7 |
|
| 世界史B | 世界史 | 3 |
|
| 日本史B | 日本史 | 3 |
|
| 地理B | 地理A | 3 |
どちらか1科目で免除可能 |
| 地理B | 3 |
||
| 現代社会 | 倫理・社会 | 2 |
両方必要 |
| 政治・経済 | 2 |
||
| 倫理 | 倫理・社会 | 2 |
|
| 政治・経済 | 政治・経済 | 2 |
|
| 数学 | 数学一般 | 6 |
どちらか1科目で免除可能 |
| 数学Ⅰ | 6 |
||
| 数学ⅡA | 4 |
||
| 数学ⅡB | 5 |
||
| 電気一般(※) | 2 |
||
| 機械一般(※) | 2 |
||
| 理科総合 | 基礎理科 | 6 |
|
| 物理Ⅰ | 物理Ⅰ | 3 |
|
| 化学Ⅰ | 化学Ⅰ | 3 |
|
| 生物Ⅰ | 生物Ⅰ | 3 |
|
| 地学Ⅰ | 地学Ⅰ | 3 |
|
| 英語 | 英語A | 9 |
免除には左記の単位数以上が必要 |
| 英語B | |||
工業数理基礎、工業数理、電気一般及び機械一般で数学の免除をする場合上記科目で「数学」を免除する場合、在籍の高等学校等で数学などがカリキュラム編成上、開講されておらず、工業数理に関する科目が数学の代替科目としてカリキュラム編成されている場合に限ります。
なお、大学入学資格検定において、既に選択科目として工業数理に合格もしくは免除の認定を受けている者は、数学を合格もしくは免除の認定を受けているものとみなします。
平成15年度4月以降入学した者で理数科の高等学校において修得した「理数数学Ⅰ」、「理数物理」、「理数化学」、「理数生物」及び「理数地学」を3単位以上修得している者は、それぞれ「数学」、「物理Ⅰ」、「化学Ⅰ」、「生物Ⅰ」及び「地学Ⅰ」が免除されます。
| 科目免除を受けることができる高等専門学校での修得単位数 | |||
| 免除を受けることが出来る受験科目 | 高等学校の科目 | 高等専門学校の 授業科目 |
免除に必要な 修得単位数 |
| 国語 | 国語表現Ⅰ |
国語に関する科目 |
3 |
| 国語総合 | |||
| 世界史A | 世界史A |
世界史に関する科目 |
2 |
| 日本史A | 日本史A |
日本史に関する科目 |
2 |
| 地理A | 地理A |
地理に関する科目 |
2 |
| 倫理 | 倫理 |
倫理に関する科目 |
2 |
| 政治・経済 | 政治・経済 |
政治・経済に関する科目 |
2 |
| 数学 | 数学Ⅰ |
数学に関する科目 |
3 |
| 物理Ⅰ | 物理Ⅰ |
物理に関する科目 |
2 |
| 化学Ⅰ | 化学Ⅰ |
化学に関する科目 |
2 |
| 生物Ⅰ | 生物Ⅰ |
生物に関する科目 |
2 |
| 地学Ⅰ | 地学Ⅰ |
地学に関する科目 |
2 |
| 英語 | オーラル・コミュニケーションⅠ |
英語に関する科目 |
3 |
| 英語Ⅰ | |||
| 科目免除を受けることができる技能審査 |
|||
| 受験科目 | 実施団体 | 名称 | 免除に相当する級 |
| 世界史B | 歴史能力検定協会 (03-5913-6407) |
歴史能力検定 | 世界史1級 又は世界史2級 |
| 日本史B | 歴史能力検定協会 (03-5913-6407) |
歴史能力検定 | 日本史1級 又は日本史2級 |
| 数学 | (財)日本数学検定協会 (03-5660-4804) |
実用数学技能検定 | 1級、準1級 又は2級 |
| 英語 | (財)日本英語検定協会 (03-3266-6555) |
実用英語技能検定 | 1級、準1級、2級 又は準2級 |
| (財)全国商業高等学校協会 (03-3357-7911) |
全商英語検定試験 | 1級又は2級 | |
| (財)日本国際連合協会 (03-3270-4731) |
国際連合公用語英語検定試験 | 特A級、A級、B級 又はC級 |
|
7単位修得証明書の手続き方法
|
科目修得証明書の手続き方法について
|
| 高等学校等で修得した単位により試験科目の免除を希望する場合は、以下の様式をダウンロードして証明書を作成し、受験願書と同封のうえ出願して下さい。 |
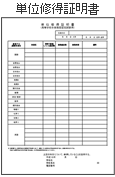 |
手続き方法 |
||||
|
「単位修得証明書」を用意する (左にあります『用紙Download』から 申請用紙をダウンロードしてください。) |
|||||
|
|
|||||
|
在籍していた学校にて 修得科目、単位を記入 して証明をしてもらう |
|||||
|
|
|||||
|
在学校で証明書交付用封筒 に入れて開封無効としてもらう |
|||||
|
|
|||||
|
願書とともに提出する |